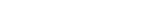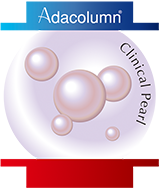兵庫県アダカラム
インタビュー記事シリーズVol. 48
IBD診療における大学病院が担う役割とGMAへの期待
兵庫医科大学 消化器内科学講座 主任教授 新﨑 信一郎 先生
近年、分子標的薬の登場によってIBDの治療選択肢が多様化した一方、患者数は年々増加傾向にあり、大学病院をはじめとした基幹病院と地域の病院との医療連携が重要視されています。大学病院では、より専門的な治療に注力するなど、各施設がそれぞれの役割を果たしていくことで、IBD患者への長期的な予後の改善が期待されます。そこで今回は、大学病院におけるIBD診療の現況と今後の展望について伺うとともに、非薬物療法であるGMAの意義についてご解説いただきました。